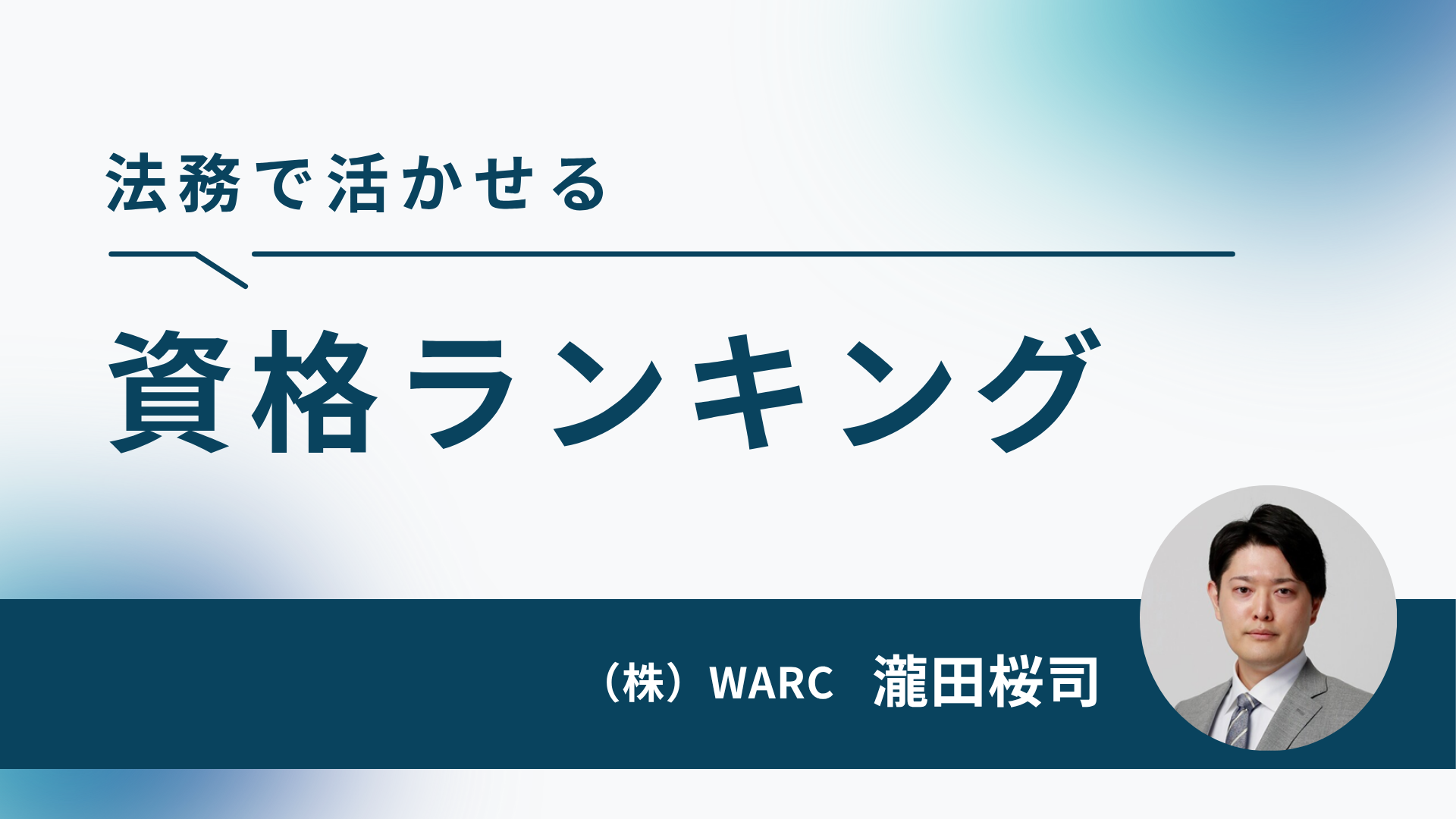
法務で活かせる資格ランキング|実務で評価される資格6選

LINEからお気軽に無料相談もできます!ご自身の転職市場価値を確認しましょう。
はじめに
企業の法務部員としてキャリアを積んでいく中で、多くの人が一度は考えるであろうテーマ、それが「専門性を高めるための資格取得」です。
日々の業務を通じて実務能力を高めていくことはもちろん重要ですが、自身の市場価値を客観的に証明し、キャリアアップの武器となる資格があれば心強いです。
しかし、世の中には数多くの法律系資格が存在し、どの資格が企業法務の実務に本当に役立ち、転職市場で評価されるのか、その実態は意外と知られていません。
難関資格であればあるほど良いという単純な話でもなく、自身の経験年数や目指すキャリアの方向性によって、その価値は大きく変わってきます。
そこで今回は、そのような疑問や悩みを持つ法務部員の方々、そしてこれから法務のキャリアを目指す方々に向けて「企業の法務部員として本当に活かせる資格」をランキング形式でまとめていきたいと思います。
1.弁護士
企業法務の世界において、弁護士資格が最強の武器であることに異論を唱える人はいないでしょう。
特に、企業法務(大手又は中堅クラスの法律事務所での経験がベスト)としての実務経験を3年以上積んだ弁護士であれば、転職市場において圧倒的な価値を発揮します。
弁護士資格がなぜ最強なのかというと、それは、企業法務が直面するあらゆる法律問題に対して、最高レベルの専門性をもって対応できるからです。
高度な英文契約のレビューやドラフティング、M&Aにおけるリーガルデューデリジェンス、複雑な訴訟や紛争への対応、そして経営層に対する的確な法的助言など、弁護士でなければ対応が困難、あるいは不可能な業務領域は数多く存在します。
これらの業務をインハウスの立場からリードできる人材は、企業にとって喉から手が出るほど欲しい存在です。
ただし、気をつけないといけないのは「企業法務の実務経験との掛け合わせ」である点です。
資格を取得したばかりで実務経験がない弁護士の場合、ビジネスの現場感覚や業界特有の慣習への理解が乏しいと判断され、ポテンシャル採用の枠に限られてしまうこともあります。
一方で、3年以上の企業法務経験があれば、ある程度ビジネスサイドの視点を持っているでしょうし、弁護士としての高度な法的知識も有しているでしょうから、その2点が融合して、その人材の価値が掛け算で評価されるようになります。
また、取得ルートとして、法科大学院(ロースクール)経由ではなく、司法試験予備試験経由で弁護士資格を取得した場合は、さらに高く評価される傾向があります。
これは、極めて合格率の低い予備試験を突破したという事実が、卓越した法的素養と、目標達成に向けた圧倒的な努力ができる人物であることの強力な証明となるからです。
たしかにインハウスローヤーの需要は少しずつ高まっていますが、その中でも企業が真に求めるのは、単なる資格保有者ではなく、事業に貢献できるビジネスパートナーとしての弁護士です。
法務実務経験を豊富に積んだ弁護士であれば、キャリアの選択肢は飛躍的に広がるでしょう。
もっとも、企業法務の実務経験が3年を超えてくると、そのまま企業法務専門の弁護士として活動した方が一般的には年収も高くなるので、わざわざインハウスに行く必要はなくなるかもしれません。
このあたりはキャリアで何を重視するかで変わってくると思いますので、贅沢な悩みとして楽しんでいただければと思います。
2.弁理士
弁護士が法務全般のスペシャリストであるとすれば、弁理士は知的財産法務のスペシャリストです。
しかも、知財分野においては、一般的な弁護士よりも遥かに専門性が高い唯一無二の資格だと思います。
現代では、IT、エンターテインメント、製造業など、多くの産業において、特許や商標、著作権といった知的財産が事業の生命線となっていますので、弁理士の需要は極めて高いと言えます。
その中でも、ビジネスに直接役に立つ分野の理系修士号又は理系博士号を持っている弁理士については特に高い評価を受けます。
そもそも弁護士は文系なので、理系分野にとても弱い傾向があります。
その点を強力に補ってくれる存在として、理系出身の弁理士が求められています。
また、企業の法務部の中に弁理士がいることの最大のメリットは、知財戦略を会社の内部から、事業戦略と一体で推進できる点にあります。
外部の特許事務所に依頼するだけでなく、自社の開発部門やマーケティング部門と密に連携し、どの技術を特許で守り、どのブランドを商標で固めるかといった出願戦略を立案する、あるいは、他社の特許権を侵害していないかのクリアランス調査や、自社の権利が侵害された際の警告・交渉、そしてライセンス契約のドラフティングや交渉まで、一気通貫で担当できます。
このような対応を社内の法務で内製化できるのは、経営者にとっては非常に有り難いことで、事業の意思決定スピードも向上しますし、有事のときの安心感も格段に変わってきます。
それゆえに高い需要があるのです。
なお、最近では、知財部門を法務部から独立させている企業もあります。
こういった会社は、知財がどれだけ大事なものなのかをよく理解していることが多いので、専門家としての意見を尊重してくれる傾向があります。
そういう意味ではとても働きやすい職場となるかもしれません。
3.司法書士
司法書士は、弁護士と比べると対応できる業務範囲に制限はあるものの、企業法務、特に会社の根幹に関わる分野において、確かな専門性と需要を誇る資格です。
その価値は、主に「商業登記」の専門知識と、会社法や民法といった「基礎的な法律知識」にあります。
そもそも企業活動において、商業登記は避けて通れない重要な手続きです。
会社の設立はもちろん、役員の就任・退任、本店の移転、増資や減資、ストックオプションの発行、そしてM&Aに伴う組織再編など、企業の重要な意思決定には必ずと言っていいほど登記手続きが伴います。
これらの手続きを外部の司法書士に丸投げするのではなく、インハウスの司法書士が主導することで、迅速かつ正確な対応が可能となり、法務部の機動力は大きく向上します。
特に、組織変更が頻繁に発生するベンチャー企業や、厳格な手続きが求められる上場準備企業において、その専門性は高く評価されます。
また、司法書士試験は会社法や民法が主要科目であるため、法律の基礎が備わっている証明として使えます。
この基礎知識は、登記業務だけでなく、日常的な契約書のレビューや作成、法務相談への初期対応といった業務においても、安定したパフォーマンスを発揮する土台となります。
弁護士のように訴訟対応をリードすることはできませんが、法務部の根幹業務である組織法務や登記関連業務を確実に遂行し、部門全体の法務レベルを底上げする存在として、司法書士は企業から一定の需要と敬意をもって迎えられる資格と言えるでしょう。
4.有名ロースクール卒
ここで挙げるのは資格ではなく「学歴」ですが、企業法務の採用市場において、これは無視できない一つの強力なブランドとして機能しています。
具体的には、司法試験に合格していなくても、東京大学、京都大学、一橋大学、神戸大学、慶應義塾大学といった、いわゆるトップクラスの法科大学院(ロースクール)の既習コースを修了した人材は、一定の評価を得られる傾向にあります。
なぜ資格ではない学歴が評価されるのかというと、それは、これらのロースクールの卒業生の法的思考力が平均的に高いとみなされているからです。
これらの上位ロースクールの既習コースでは、入学時点である程度広い法律知識と論述力が求められます。
そして、2年間の厳しいカリキュラムを修了したことで「最低限の法的思考力と法律知識を習得している」と見なされるため、転職市場でも一定の評価を受けています。
ロースクールにおいて、膨大な量の判例や文献を読み解き、複雑な事案を分析し、論理的な文章を構築するという作業を2年間みっちりと行う経験は、たとえ司法試験に合格しなかったとしても、その人の思考力を飛躍的に高めます。
司法試験に合格できなかったことはたしかに残念なことではあるのですが、過去に積み重ねた努力はきちんと評価されているので、法務専門職への道を諦めずに挑戦してみると良いと思っています。
ただし、この学歴が武器として真価を発揮するためには、重要な前提条件があります。
それは「3年以上の法務実務経験」です。
最近では「5年以上」を要求する会社も増えてきているので、徐々に厳しくなっていっている状況です。
したがって、実務経験のないロースクール修了生は、残念ながらそこまで求められていませんので、すぐに就職で評価されるという構造にはなっていません。
あくまでも、法務経験を積んだことによって、掛け合わせで評価されやすくなるという状態です。
5.行政書士(法務事務)
行政書士資格は、その業務範囲の特性から、企業の法務部員としてキャリアの中核を担うには、少し弱い側面があることは否めません。
行政書士の主な業務は、官公署に提出する許認可等の書類作成とその代理であり、企業法務のメイン業務である契約レビューや紛争対応、組織法務とは直接的に重なる部分が少ないからです。
しかし、視点を変えて「法務事務」という職種に注目すると、この資格の価値は大きく高まります。
法務部が円滑に機能するためには、専門的な判断を担う法務部員だけでなく、彼らを支える事務・管理業務が不可欠です。
契約書の製本・管理、捺印申請の受付・処理、登記簿謄本や印鑑証明書の取得、許認可の更新管理、社内規程の管理といった業務は、まさに法務事務の守備範囲であり、行政書士の受験で得た法律の基礎知識を活かせる場面でもあります。
採用する企業側から見ても、全くの未経験者を採用するより、行政書士資格の保有者の方が、基本的な法律用語や手続きの流れを理解しているため、教育コストが低く、早期に戦力化できるというメリットがあります。
法務部員としての採用は難しくとも、法務部門への入り口である「法務事務」としてキャリアをスタートさせるための有効な資格です。
6.ビジネス実務法務検定2級以上(法務事務)
ビジネス実務法務検定は、法務部員としての専門性を示す上では、これまで紹介してきた国家資格に比べて見劣りする点は否めません。
しかし、この検定試験も、特に「法務事務」のポジションを目指す上では、自身の知識と意欲を証明する有効なツールとなり得ます。
この検定が評価されるのは、法律知識がゼロの人材との差別化を図れる点にあります。
特に法学部出身でない方や、他職種から未経験で法務関連の仕事に挑戦したい方にとって「ビジネス実務法務検定2級」は、民法や会社法といった企業活動に必要な法律の基礎知識を、体系的に学習したことの客観的な証明となります。
採用担当者からすれば、数多くの応募者の中から、少なくとも法務事務という仕事への興味関心と、自ら学んで知識を習得するだけの意欲がある人材を見つけ出すための一つの指標となります。
もちろん「この検定を持っていれば高く評価される」という類の強力な武器ではありませんので、あくまで、最低限の知識レベルを証明し、キャリアのスタートラインに立つためのアピール材料と捉えるのが現実的です。
それでも、何も持っていない状態から一歩を踏み出し、法務の世界への扉を叩くための最初の一歩として、その価値は決して小さくありません。
行政書士と同様に、法務事務としての就職・転職を目指す際の有力な選択肢の一つとなるはずです。
おわりに
以上が法務として活かせる資格です。
この記事が皆様のお役に立てば幸いです。
法務の転職なら「WARC AGENT」の無料カウンセリングへ!

「WARC AGENT」なら、大手上場企業からIPO準備企業のベンチャー求人まで幅広く対応しています。
業界トップクラスの転職実績もあり、業界に精通しているエージェントも多数在籍していますので、ぜひ気軽にご相談ください!
LINEで簡単転職相談もお受付しています!

LINEからお気軽に無料相談もできます!ご自身の転職市場価値を確認しましょう。

