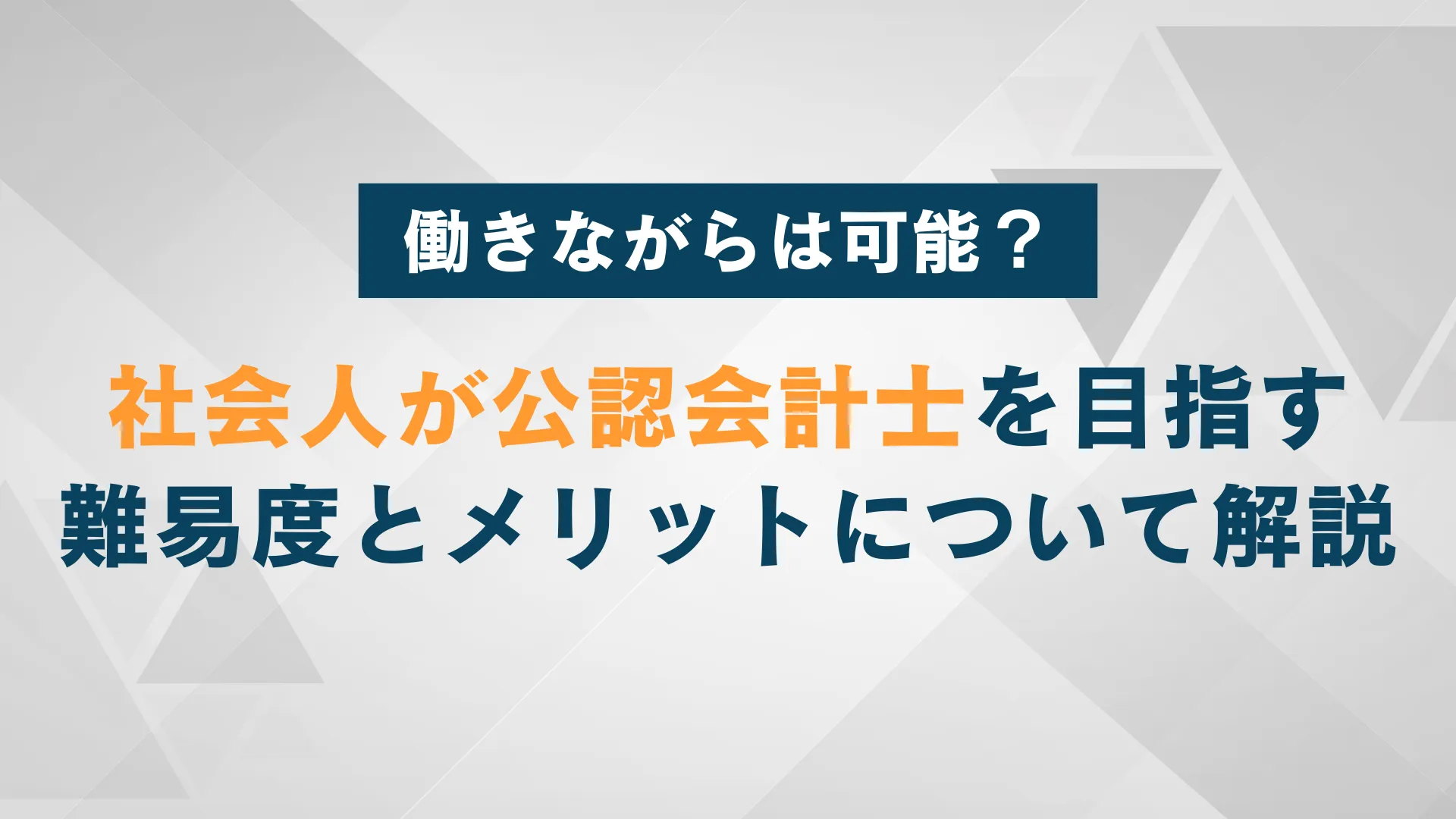
働きながらは可能?社会人が公認会計士を目指す際の難易度とメリットについて解説

LINEからお気軽に無料相談もできます!ご自身の転職市場価値を確認しましょう。
公認会計士は社会人にとって難易度は高いのか?
公認会計士試験の難易度に焦点を当ててみましょう。公認会計士試験は最難関とされ、合格にはかなりの難易度が伴います。合格を目指す際には、その難易度を理解し、効果的な対策を講じることが重要です。
参考:公認会計士とは?|資格を取得する方法や仕事内容、年収・やりがい・将来について解説
社会人であっても可能性がある
社会人であっても、公認会計士試験に合格することは可能です。
社会人が公認会計士を目指す場合、適切な勉強時間を確保できず難しいと感じることが一般的でしょう。しかし、毎年多くの社会人が公認会計士試験に合格しています。
社会人向けに提供されている通信講座やオンラインスクールを利用することで、合格を目指す人が多いです。これらの社会人向けコースを活用することで、公認会計士試験に効率的に備えることができます。
加えて、公認会計士になるためには監査法人に転職することも一つの方法です。監査法人は、公認会計士試験に合格していなくても転職が可能であり、実務経験を積みながら勉強する社会人も多数います。実務経験を積むことで、公認会計士に対する理解が深まり、勉強時間の短縮につながるでしょう。
さらに、理解のある監査法人や会計事務所では、受験生へのサポートが期待できます。特に、休暇取得や残業免除などの配慮がある場合もあり、監査トレーニー制度を提供する法人も多いです。これらの環境を活かし、公認会計士を目指してみましょう。
社会人の公認会計士試験合格率
社会人の公認会計士試験合格率は約4〜5%(※1)です。
全体的な合格率が9.6%(※1)であることを考えると、社会人の合格率は低い傾向にあります。学生と比較すると、学生は勉強時間に制約がないため、合格率が高い傾向です。しかし、社会人も全く合格できないわけではなく、コツコツと毎日勉強することで公認会計士に合格することができます。
社会人の合格率を見れば、20人に1人は合格していることがわかるでしょう。時間が限られている社会人でも、着実に勉強を進めることで、公認会計士に合格できます
(※1)参考:金融庁「公認会計士試験 合格者調」
独学は厳しい
公認会計士試験は独学でも受験可能ですが、おすすめはできません。
独学をおすすめしない理由は以下の通りです。
- 勉強効率が悪い
- 時間の使い方が非効率的
- 計画的な勉強が難しい
独学では、過去問やデータの分析を通じて勉強を始める必要があります。そのため、試験対策以外にも多くの時間がかかり、効果が低いです。また、自分でデータを分析する場合、素人の視点からの分析であり、試験問題に適しているかどうかが確証できません。
一方で、通信講座やオンラインスクールを利用すれば、公認会計士試験に特化した講師陣が作成したテキストを利用できます。過去問やデータ収集についても講師が代行し、迅速に学習を始めることが可能です。
また、理解できない点が生じた場合、講師にすぐに質問できるのも利点でしょう。独学の場合、理解できない部分を自力で解決する必要がありますが、講師に質問できれば、わかりやすい説明に基づいて理解が進みます。
社会人が公認会計士試験に取り組む3つの手段
社会人が公認会計士試験に挑戦する方法を詳しく説明します。
これらの方法を把握し、自身に合ったアプローチで試験に挑戦してみましょう。
①自己学習
社会人の中には、予備校や通信講座に参加する時間が取れない人も多いです。そのような場合、自己学習が一つの選択肢となります。
仕事の都合や予算の制約から予備校通いが難しい方にとって、DVDやYouTubeなどで提供されている無料講座を活用が可能です。自己学習の利点は、自分のペースで学習でき、時間に縛られないことでしょう。したがって、社会人でも仕事と両立しながら、自由度高く勉強を進めることができます。
②通信講座
通信講座は、予備校に通う必要がなく、オンラインで授業を受けることが可能です。通信講座は予備校と同様に優れた教材を提供しており、自己学習よりも効率的な学習が期待できます。また、通信講座は自分の都合に合わせて学習できるため、忙しい社会人にとって都合が良いでしょう。
最近では、スマートフォンやタブレットを利用した動画コンテンツが充実しており、通勤時間や空き時間を活用して効果的に学習できます。通信講座では講師に質問できるため、初めて公認会計士の勉強を始める方も安心して進められるでしょう。
③予備校や専門学校
公認会計士の勉強を初めて取り組む方や、単独で学習する際にモチベーションが上がりにくい方には、予備校通いがおすすめです。
予備校では一流の講師から直接学べ、公認会計士に対する理解が他の学習方法よりも理解が早く深まります。また、同じ目標を持つ受験者とともに学習でき、モチベーションを保ちながら進めることが可能です。予備校では合格に向けた高品質な教材が提供されているため、確実に目標を達成できます。
公認会計士試験合格に必要な勉強時間
公認会計士の資格を取得するためには、3,000時間以上の勉強が必要です。つまり、1日5時間から6時間ずつ勉強しても、1年半から2年以上の期間が必要と考えられます。
公認会計士の試験内容は非常に広範で深いため、相当な勉強時間がかかると認識しておきましょう。もちろん、1年で合格する方や、既に会計知識がある方はその分勉強にかかる時間を短縮できます。
社会人が公認会計士試験に合格する3つのアプローチ
では、公認会計士を目指しながらも忙しい社会人がモチベーションを保ち続ける方法について、どのような点に注意するべきでしょうか。
以下では、社会人が公認会計士試験に合格するための3つのアプローチについて説明します。これらのアプローチを考慮することで、モチベーションを維持しやすくなりますので、ぜひ参考にしてください。
アプローチ1:効率的な勉強
忙しい社会人は、勉強の際に効率を重視することが重要です。
自由に使える時間が限られている社会人は、毎日の短い時間を有効活用する必要があります。そのためには、移動時間や外出中にも勉強できるように環境を整えることが重要です。
スマートフォンやタブレットを利用したデジタルコンテンツがいいでしょう。場所を選ばず、動画を視聴しながら理解を深めることができます。
また、勉強内容を工夫することも重要です。自身の苦手分野に特化したテキストで重点的に学習したり、試験で高頻度に出題される部分をまとめたテキストで効果的に学習することが可能です。
アプローチ2:持続可能な習慣
社会人が仕事と両立しながら公認会計士の合格を目指すには、持続可能な習慣が不可欠です。
多くの社会人が、勉強時間を確保することが難しくなり、いつの間にか試験の目標を諦めてしまうことがあります。仕事の忙しさや計画的な学習の難しさは、社会人にとっては当然のことです。
しかし、諦めずに、自分のペースに合わせた計画を修正することを意識しましょう。無理のない範囲で計画を立て直し、着実に進捗することが、公認会計士に合格するための秘訣と言えます。
最初はハイペースで進める計画よりも、毎日確保できる1時間でもコツコツと続けることが重要です。この日々の積み重ねこそが、公認会計士の合格へつながるので、自身のペースでコツコツと学習を続けるようにしましょう。
アプローチ3:隙間時間の有効活用
社会人の方々は時間が不足していると感じることが一般的ですが、その中で見落としがちなのが隙間時間です。
朝晩の通勤時間や昼休憩、帰宅後から寝るまでの時間など、生活の中には様々な隙間時間が存在します。これらの時間を有効に活用することは、社会人にとって非常に重要です。
隙間時間には、オンライン講座やデジタルテキストが適しています。これらはスマートフォンを使って手軽に学習できるため、電車やバスの移動中や昼休憩の合間にも気軽に勉強可能です。
特に通勤時間が長い方や外回りの業務が多い方にとっては、隙間時間の有効活用が非常に効果的でしょう。通勤中に音楽を聴くのではなく、オンライン講座を活用して学びの時間に変えてみることをおすすめします。
ただし、社会人が1日5時間以上勉強することは容易ではありません。毎日仕事が終わった後に、5時間もの勉強時間を確保し続けることはかなり負担です。その上、それを1年以上続けるのは、モチベーションの維持が難しく、公認会計士の合格を諦める人も多いでしょう。
社会人が公認会計士に合格するためには、モチベーションを持続させることが肝心です。公認会計士を目指す社会人は、以下に示す方法でモチベーションを保ちつつ合格を目指しましょう。
働きながら公認会計士を目指す3つの利点
忙しい社会人が、膨大な勉強時間を確保しつつも公認会計士を目指すことには、大きな利点があります。
以下では、公認会計士を目指す際の利点を3つ紹介するので、公認会計士に興味を持つ方は、これらの利点を読んで勉強への意欲を高めてください。
利点1:収入の向上が期待できる
公認会計士は、高い収入が見込めると言われています。
厚生労働省が20歳から65歳までの人々を対象に行った調査によると、公認会計士の平均年収は1,010万円(※2)でした。一般的に、日本で働くサラリーマンの平均年収は約450万円(※2)とされているため、公認会計士の収入は2倍以上も高いことが分かります。
大手監査法人に所属する公認会計士ならば、初年度の平均年収は500万円から650万円とも言われており、初年度から高収入を期待できます。
一部の公認会計士は、年収が1,000万円を超えることもあり、公認会計士の収入水準は一般的に非常に高いと言えるでしょう。
(※2)参考:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」
利点2:試験内容の理解が容易
公認会計士試験の内容は、ビジネスで必要な会計に関する問題が中心です。
そのため、公認会計士でなくても、社会人であれば日々の業務で出会うシチュエーションを想像することで、公認会計士試験の内容を理解しやすくなります。
新入社員など、ビジネス会計の基礎知識がない学生とは異なり、社会人は一定のビジネス会計の知識を有していることが一般的です。そのため、学生時代よりも公認会計士試験の内容を理解しやすくなります。
また、実践的なイメージがあると理解が深まりやすいため、社会人は学生よりも理解を進めやすく、公認会計士を目指しやすい環境にあるでしょう。
利点3:実務経験の積み重ね
公認会計士試験に合格していなくても、監査法人や会計事務所で働くことができます。そのため、社会人は実務経験を積みながら勉強することができ、知識の吸収が容易です。
公認会計士を目指す人の中には、監査法人や会計事務所で働きながら、公認会計士の知識を増やしている人も増えています。これらの方々は、日々実務を行いながら公認会計士の知識を積み重ねているのです。当然ながら、収入も得ることができます。
公認会計士試験の内容は幅広く、知識の習得だけでは理解が難しいものです。理解を深めるためには、アウトプットも欠かせません。社会人であれば、査法人や会計事務所での実務経験を通じてアウトプットが可能であり、知識を深めやすい環境が整っています。
実務経験は、試験の出題内容に対するイメージが湧きやすく、公認会計士試験の合格にも寄与することでしょう。
勉強と仕事が両立できる職場の特徴
公認会計士試験に向けて仕事と勉強を両立させるためには、適切な職場選びが不可欠です。
仕事と勉強を両立するための職場の特徴を紹介します。以下の特徴を考慮して、職場選びの際に参考にしてください。
1. 残業時間が少ない
公認会計士試験合格には、十分な勉強時間が必要です。そのため、残業時間が少ない職場を選ぶことが重要です。
一般的に、残業が少ない職種には、経理や会計などのバックオフィス職があります。企業によって異なりますが、残業が少ない環境であれば、仕事後に勉強時間を確保しやすくなるでしょう。
一方で、ベンチャー企業や外資系企業は残業が多い傾向にあります。特に外資系企業では、海外との打ち合わせなどで残業が頻繁に発生する可能性が高いです。残業が多いと勉強時間を確保するのが難しくなるため、残業が少ない職場を選ぶようにしてください。
2. 公認会計士試験に理解がある職場
すでに公認会計士試験を受験した経験がある職場では、試験に対する理解が深まります。そのため、試験前に休暇を取得しやすく、勉強時間を確保しやすくなるでしょう。
また、公認会計士試験を受験した経験がある人が職場にいれば、彼らからの助言やアドバイスを受けることができます。経験者の助言は、受験者にとって非常に有益です。
さらに、同じ職場に公認会計士試験を受験する同僚がいれば、互いに切磋琢磨しながら勉強を進めることができます。公認会計士試験には多くの時間と努力が必要ですが、理解のある職場であればモチベーションを維持しやすくなります。
3. 仕事内容と試験内容が関連している職場
会計事務所や経理部門などの職場では、公認会計士試験の内容と仕事内容が密接に関連しています。そのため、仕事を通じて公認会計士試験の知識を身につけることが可能です。
座学だけでなく、実務経験を通じて学習することは非常に効果的でしょう。会計事務所や経理部門での経験は、公認会計士試験の勉強に役立ちます。
仕事終わりに勉強時間を確保できない場合は、会計事務所や経理部門などで働くことを検討してみてください。また、転職エージェントを活用して、公認会計士試験を目指す社会人向けの職場を探すこともおすすめです。
公認会計士の転職は転職エージェントを利用
会計事務所や経理への転職におすすめなのが転職エージェントの利用です。
日中働きながら、転職活動も勉強も両立させると考えると、かなり時間がかかり効率が悪くなります。公認会計士への転職を目指している方は、勉強時間を十分に確保するためにも、転職活動ではプロのサポートを受けるようにしましょう。
転職エージェントの中には、サービスに登録後、自分の経歴や経験を掲載しておくと企業からスカウトが届くサービスもあります。自分から企業を探しに行かなくても、あなたの経験に興味を持った企業からスカウトが届くため、転職活動にかける時間を大幅に削減可能です。
また、アンケートに回答すればシステムがあなたの市場価値を診断してくれるサービスもあります。自分の現在の市場価値を理解することで、転職先や仕事内容のミスマッチを防げるのでおすすめです。
市場価値を理解することは、転職活動以外にも自身のスキルアップを見直す際にも重要なので、積極的に転職エージェンㇳを活用してみましょう。
社会人の公認会計士に関する質問に回答
社会人の方に向けた公認会計士に関する質問と回答です。同じ悩みを持つ方は、以下の回答を参考にしてみてください。
1. 働きながらの公認会計士試験は何年かかりますか?
公認会計士試験合格には、毎日の勉強が欠かせません。社会人が毎日5時間以上の勉強時間を確保するのは難しいですが、1日2時間は効果的です。休日には通常より多くの勉強時間を確保し、合格までの年数を短縮できます。
また、働く環境によっては公認会計士の業務に関連する経験を積めるため、知識のインプットが可能です。これにより、勉強時間以外にも効果的な準備ができ、モチベーションを維持しながら合格を目指してください。
2. 公認会計士と税理士、どちらがいいですか?
公認会計士と税理士には優劣はありませんが、公認会計士は税理士登録も可能です。税理士は税務関連の業務を担当しますが、公認会計士は主に監査業務が中心になります。どちらかに迷っている場合は、公認会計士を目指すのがおすすめです。なぜなら、公認会計士であれば税理士登録も可能であり、選択肢が広がります。自身のキャリアややりたい業務を考慮し、合格に向けて効率的に勉強を進めてください。
3. 30代でも公認会計士を目指せますか?
公認会計士には年齢制限がありません。そのため、30代でも公認会計士を目指せます。
歴代の30代公認会計士試験合格者割合です。
▼30代~34歳(30代前半)
2017年:合格者160人/合格率8.9%(論文合格率27.8%)
2018年:合格者123人/合格率6.8%(論文合格率21.7%)
2019年:合格者142人/合格率8.1%(論文合格率25.6%)
▼35代~39歳(30代後半)
2017年:合格者58人/合格率5.3%(論文合格率18.5%)
2018年:合格者51人/合格率4.4%(論文合格率14.8%)
2019年:合格者58人/合格率5.0%(論文合格率16.2%)
30代前半であれば、平均合格者数は8%(※3)で、12人に1人が合格しています。一方で、30代後半だと平均合格者数は5%(※3)で、20人に1人が合格していることがわかります。30代全体でみると、20%が合格占有率であり、5人に1人は合格しているため、合格率は高いといえます。
上記の結果からわかるとおり、30代でも積極的に公認会計士を狙えるでしょう。
(※3)参考:公認会計士試験 合格者調
転職エージェントを利用して効率的に公認会計士を目指そう
公認会計士試験は時間がかかるため、転職活動も効率的に進めることが重要です。転職エージェントを利用することで、プロのサポートを受けながら希望の職場を見つけることができます。転職エージェンㇳの利用は忙しい社会人におすすめです。
公認会計士の転職なら「WARC AGENT」の無料カウンセリングへ!

「WARC AGENT」なら、大手上場企業からIPO準備企業のベンチャー求人まで幅広く対応しています。
業界トップクラスの転職実績もあり、業界に精通しているエージェントも多数在籍していますので、ぜひ気軽にご相談ください!
LINEで簡単転職相談もお受付しています!

LINEからお気軽に無料相談もできます!ご自身の転職市場価値を確認しましょう。
