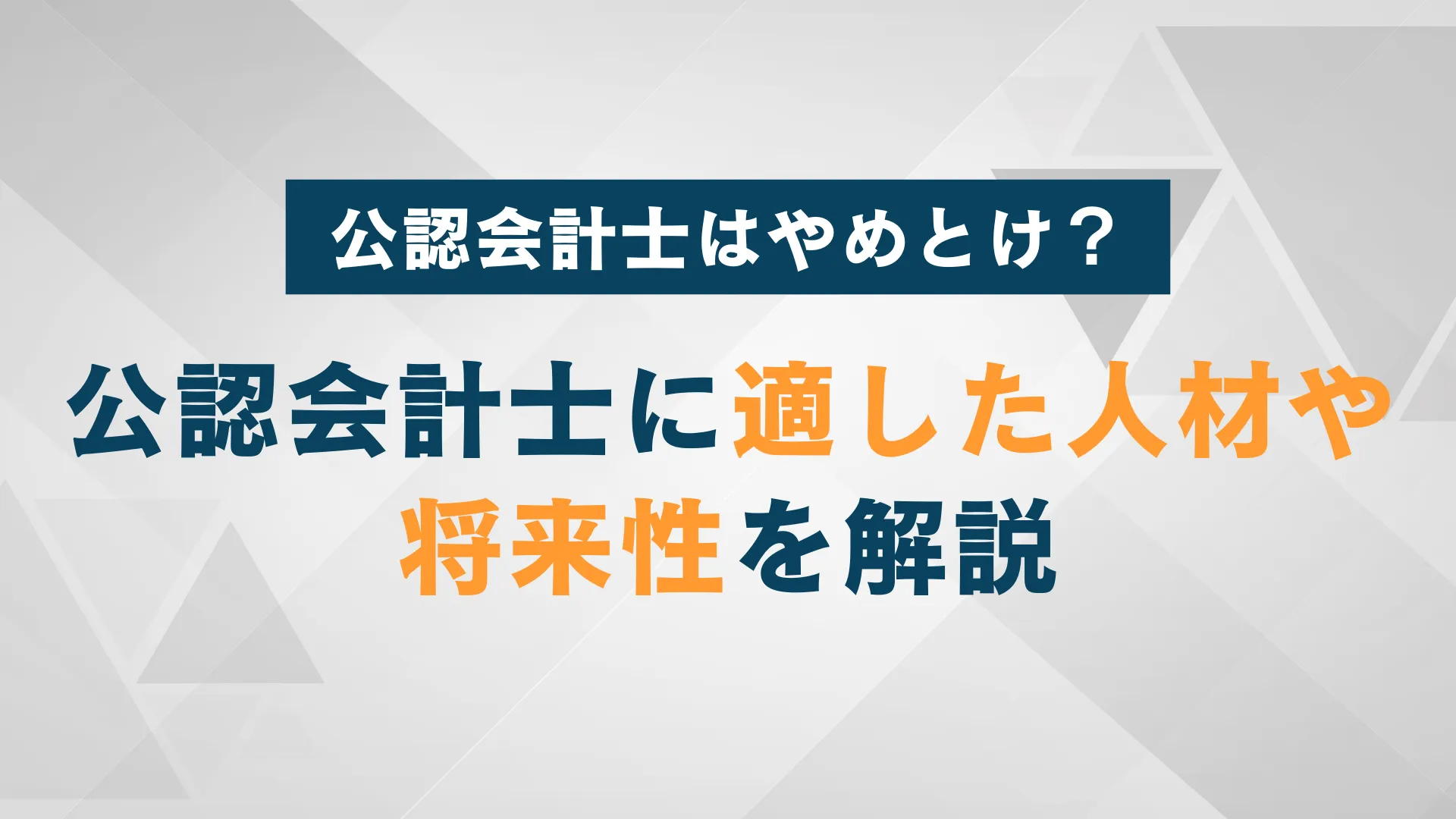
公認会計士は「やめとけ」ってほんと?公認会計士に適した人材や公認会計士の将来性を解説

LINEからお気軽に無料相談もできます!ご自身の転職市場価値を確認しましょう。
年収が魅力的で輝かしいイメージから公認会計士に関心を持った人も多いかと思いますが、「公認会計士はやめとけ」という言葉を耳にしたこともあるでしょう。公認会計士資格は三大国家資格に含まれていますが、果たして本当に避けるべきなのか、疑問が湧いてくる人も多いはず。
この記事では、公認会計士向きの人物、避けるべき理由、そして将来の展望について解説しています。記事を参考に、公認会計士について詳細に理解し、デメリットを把握した上で転職を考えてみましょう。
公認会計士とは何か?
まずは、公認会計士の職業内容について確認してみましょう。
公認会計士は、監査や会計の専門家です。彼らは経済システムの健全性を維持し、人々が経済活動を安心して行えるように、「企業の財務情報の信頼性を保証する」という社会的責務を担っています。彼らは「監査」という独占業務を行うだけでなく、税務処理やコンサルティングなども担う場面が多いです。
お金の動きがある場所には必ず会計が存在し、会計があるということは必ず監査が必要とされます。公認会計士は経済社会の様々な分野で活躍する機会があり、その能力の適用範囲の広さが魅力です。彼らは監査業務や株式公開のサポート、ビジネスアドバイザリーとしての活動、独立開業、組織内での会計士としてなど、多岐にわたる働き方を実現できる職業でもあります。
公認会計士を避けるべき理由5つ
公認会計士は会計の専門家として経済社会に貢献できる魅力的な職業ですが、「公認会計士を目指すのは避けるべき」「公認会計士はおすすめできない」という否定的な意見も多く見られます。
この場で公認会計士を避けるべき理由や、公認会計士として実際に仕事を始めた場合の現実について解説します。
① 公認会計士になるための試験難易度が高すぎる
公認会計士がお勧めされない理由の中で、最も頻繁に挙げられるのは試験の難易度の高さです。
公認会計士は医師や弁護士と同様に、三大国家資格の一つである専門職です。そのため、資格試験の難易度も国内最高水準であり、受験者が勉強に費やす労力が非常に大変だという理由から、「公認会計士は避けた方がいい」という声が上がることがあります。
実際、2022年度の最終的な合格率は7.7%(1,456人)(※1)であり、非常に厳しいことが分かります。また、受験に際しては年齢や学歴に関係なく、短答式試験や論文式試験など、すべての科目を一度に受験しなければなりません。
それゆえ、複数の科目を同時に勉強する必要があります。学生なら比較的時間を取りやすいかもしれませんが、仕事と勉強を同時にこなさなければならない社会人にとっては、非常に厳しいスケジュールとなるでしょう。
2022年度の合格者の内訳を見ると、「学生」や「専修学校・各種学校受講生」が全体の66.1%を占めていますが、会社員は6.5%と非常に少ないことが分かります。
(※1)参考:令和4年公認会計士試験の合格発表の概要について
② 仕事が単調な場合もある
公認会計士の仕事はどれも責任を伴う重要なものですが、一方で、やりがいを感じにくい公認会計士も多く存在するようです。
公認会計士の仕事でやりがいを感じにくい理由の中で、よく挙げられるのが「事務作業の単調さ」でした。公認会計士の独占業務である財務諸表の監査は、クライアントの財務諸表の誤りをチェックし、その内容を保証する作業です。この事務作業が面白みのない単調な作業だと感じる会計士が一定数います。他の業務も基本的に数字と向き合う仕事なので、「一生懸命公認会計士になったけれど、なんだか地味でつまらない」と感じることもあるかもしれません。
マネージャーになればより複雑な問題に取り組む機会も増えるでしょう。しかし、多くの公認会計士は主に事務作業に従事している実態です。
③ 監査法人の業務は激務
前述の通り、仕事が単調なだけであれば乗り切れる可能性もありますが、会計監査は極めて忙しい状況です。
特に監査法人で働く場合、上場企業の多くが3月に決算を行うため、4~5月の決算期は非常に忙しい時期になります。公認会計士はしばしば「季節労働者」と言われているほどです。この時期は書類チェックなどの量が膨大になり、深夜労働や週末出勤が頻繁に発生します。月に100時間以上の残業が珍しくありません。
最近ではワーク・ライフ・バランスや36協定の意識が高まっており、遅い時間になるとPCを強制的にシャットダウンさせるなどの取り組みが行われていますが、繁忙期は非常に忙しいことが実情です。逆に、8月や11月は閑散期に当たり、メリハリをつけて働きたいと考える人には適しています。
④ パートナーになるのが困難
パートナーとは監査法人の共同経営者です。監査法人は5人以上の公認会計士が出資して設立される法人であり、パートナーは監査法人への出資者を指します。要するに法人の幹部であり、会計監査の責任者です。一般的にパートナーに昇格するのはおよそ10人に1人と言われており、会計士として15~18年程度の経験が必要とされています。
パートナーになるためには、会計に限らず別の資質や能力も求められます。厳しいですが、地道に監査実務をこなしても必ずしもパートナーになれるわけではないのが実態です。
責任者としての責任感や強いメンタル、クライアントや従業員からの信頼を得るコミュニケーション能力や人間的な魅力も求められます。また、管理職としては、チームをまとめるリーダーシップも必要不可欠です。
⑤ AIへの切り替え
会計監査はコンピューター技術との相性が高く、将来的には約80%がAIに取って代わると予想されています。定型作業の自動化や財務情報のデータ分析はAIによって行われ、業務の効率化や監査の品質向上が期待されています。そのため、公認会計士が不要になるのではないかとの懸念があります。
しかしながら、複雑な会計論点の検討や総合的な判断には人間の介入が必要です。むしろAIに事務作業を任せることで、決算時期の多忙さが緩和されたり、専門家としての判断を要する経営コンサルティングなどの業務に時間を費やすことができるでしょう。セキュリティ面でも、機密情報の漏洩リスクが高いため、AIに全てを任せることは難しいです。そのため公認会計士の存在意義は継続されると考えられます。
公認会計士の魅力とやりがい
これまでに「公認会計士は避けるべき」という否定的な理由を挙げてきましたが、公認会計士には良い側面も存在します。公認会計士を目指すかどうか迷っている場合は、長所と短所の両方を考慮して判断することが大切です。
この節では、一般に知られているものからあまり注目されていないポイントまで、公認会計士の魅力と仕事のやりがいを紹介します。
安定した高収入
公認会計士の収入は非常に魅力的であり、多くの人が高収入を求めて公認会計士の道を選んでいる人も多いはず。
厚生労働省の「令和4年賃金構造基本統計調査」によれば、公認会計士や税理士の平均年収は746万6,400円(※2)です。これは一般の労働者の平均年収である311万8,000円の2倍以上です。
役職別に見てみると、監査法人によって異なりますが、スタッフ1年目の基本給は月額30万円以上とされています。これにボーナスと残業代が付与され、年収は約600万円になると言われています。新卒1年目の給与としては非常に高水準です。
約4年目でシニアスタッフに昇進すれば年収は900万円程度、約8年目でマネージャーになれば1,000万円、更にパートナーになれば1,500万円程度とされています。
(※2)参考:令和4年賃金構造基本統計調査 結果の概況|厚生労働省
独占業務
会計監査業務は公認会計士のみが行うことができる独占業務です。公認会計士は企業の財務書類を監査し、その適正性を証明する唯一の職業でもあります。上場企業や一定の要件を満たす大規模な企業は監査を受ける必要があり、公認会計士の存在が極めて重要です。
監査業務には「法定監査」と「任意監査」の2つがあります。法定監査は金融商品取引法や会社法などの法令に基づいて義務付けられるものであり、任意監査は法定監査以外の監査全般を指します。企業の自発的な監査や第三者による監査にも公認会計士が必要とされるため、需要が確保されている点が魅力的です。
責任は重大ですが、その分やりがいを感じることができるでしょう。
社会的信用度が高い
公認会計士は医師や弁護士と並んで三大国家資格に位置づけられている専門職です。公認会計士の名前を聞くだけで、「賢そう」「優秀そう」という印象を抱く方も多いでしょう。
特に魅力的なのは、学歴に関係なく「公認会計士」という肩書を手に入れられることです。国家資格試験に合格すれば、短期間で高い社会的信用を得ることができます。さらに監査法人で働いている場合、信用度はさらに高まるでしょう。融資やローンの取得も容易になるでしょう。
異業種への転職を考える際にも、公認会計士の資格は強力な武器となります。難関国家資格を持つことで、真面目で信頼できる人材であるという印象を与えられるでしょう。
男女の区別なく活躍可能
公認会計士は男女差別がなく、能力に応じた評価が受けられるため、女性が活躍しやすい職業です。育児や家事との両立がしやすいだけでなく、育児休暇を取得して仕事を離れた後も、スムーズに復帰できる環境が整備されています。キャリアが途切れがちな女性にとって、職場復帰のしやすさは魅力的です。
日本公認会計士協会では、女性会計士の活躍を推進するための取り組みを積極的に行っています。「2030年までに公認会計士試験合格者の女性比率を30%にする」「2048年度の公認会計士制度100周年までに、会員と準会員の女性比率を30%にする」という2つの目標を掲げており、2016年には協会の会長に初めて女性が就任しました。これからも女性の活躍がますます期待されています。
会社の経営に参画できる
公認会計士は監査業務を通じて企業の財務情報を精査します。また、会計の専門知識を活かしてクライアントの問題解決に貢献し、時には会社の重要な決定に関与することもあります。キャリアを積んでいくと、企業の経営陣と共に経営戦略について議論する場面も多くなるでしょう。公認会計士は外部の専門家でありながら、クライアント企業の経営に深く関わることができる点が魅力のひとつです。
監査法人のパートナーという目標を持つ多くの公認会計士は、監査法人の共同経営者を指します。こうした立場にいると、会計だけでなく経営全般について成長し、新たなやりがいを見出すことが可能です。また経営に深く関わることで、会計業務だけにとどまらず経営コンサルティングなどへの展開もできます。
キャリアの幅が広がる
公認会計士試験では、「財務会計」「経営」「税務」といった幅広い分野の知識を同時に身につけます。このような幅広い知識を持つことは、資格が証明してくれることで、働き方に大きな選択肢をもたらす効果があります。
例えば、公認会計士の資格があれば税理士登録も可能になり、税理士としての活動ができます。また財務会計や経営の知識を生かして、コンサルティング業界で活躍することも可能です。さらに、「公認会計士になったけれど、監査業務が合わなかった」という場合でも、キャリアパスの多様性があります。
企業に所属するだけでなく、独立したりフリーランスとして活動することも容易な職業です。自らスケジュールや仕事量を調整できるため、自由な働き方を実現しながら、ワークライフバランスを保つ公認会計士も増えてきています。
公認会計士に適した人材
公認会計士に適した人物はどのような方でしょうか。多くの職業と同様に、公認会計士にも向き不向きが存在します。実際、「会計」という専門性の高い分野に従事するため、向き不向きの影響が比較的大きいと言えるでしょう。
ここでは公認会計士に適した人材の特性について詳しく説明します。公認会計士の道は「やめとけ」と否定的に言われることもありますが、もし自身が公認会計士向きの特性を持っていると判断できれば、十分にチャレンジする価値があるでしょう。
根気のある方
公認会計士の道は難関であることが先に述べた通りです。この資格を獲得するためには、忍耐強さが必要不可欠でしょう。
公認会計士として活動を始めた後も、忍耐強さが求められます。一般的に、黙々と地道なデスクワークが基本です。このため、コツコツとした作業が好きな方や地道な業務に耐えられる方が向いているでしょう。
高収入や社会的な信用を得るといったイメージがあるかもしれませんが、公認会計士は企業の基盤を支える役割を果たしています。一つのことに集中し、最後まで粘り強く取り組むことができる方が公認会計士として向いていると言えます。
正確に業務を遂行できる方
公認会計士の役割は企業の財務情報の正確性と信頼性を保証することです。高度な専門知識だけでなく、業務の正確性が重視されます。
公認会計士は主に財務諸表の監査を行いますが、これらの数字は企業の状態を示しています。また、財務諸表の数字から虚偽を見破る必要もあり、非常に細かい数字に敏感であることが求められます。
自分の仕事が企業や社会に与える影響を理解し、責任を持って正確に業務を遂行することが重要です。厳密に仕事をこなし、正確性に対してモチベーションを感じる方が公認会計士に向いています。
数字やITに強い方
公認会計士の仕事は基本的に数字と関わるものです。数字に強い方は、財務諸表のチェックなど公認会計士の業務をスムーズにこなせるでしょう。数字に苦手意識がなく、企業の数値を理解する能力が求められます。数字に苦手意識を感じる方は、公認会計士には向いていない可能性があります。
また、公認会計士における「数字に強い」とは、数学のスキルよりも数字を活用して物事を考える能力をいいます。財務諸表は企業活動を数字で表現したものなので、数字を用いて企業活動を理解する能力が重要です。また、IT化により、内部統制や会計の分野でのIT知識も求められます。
コミュニケーションスキルが高い方
公認会計士の主な業務である監査はチームワークを必要とし、仲間と協力して業務を進めることが重要です。財務諸表に取り組むだけでなく、現場での資料調査やクライアントとのやり取りも含まれます。さらに、独立したり開業する際には自ら顧客を獲得する営業スキルが不可欠です。
公認会計士はチームやクライアントとの信頼関係構築が欠かせない職業ともいえます。経営陣や取引先とのコミュニケーションにおいて、的確に伝えたり理解したりするスキルがあれば、業務が円滑に進むでしょう。したがって、コミュニケーション能力は非常に重要です。
論理的思考ができる方
公認会計士は数字を取り扱うため、論理的な思考能力が必要です。
論理的思考とは、物事の因果関係を整理し、筋道を立てて考える能力のことを言います。会計業務では客観的な判断が求められるため、論理的思考能力が必要です。このようなスキルがあれば、公認会計士向きと言えます。
ロジカルシンキングは学習を通じて身につけることもできますが、すでに論理的思考が身についている方が有利です。自分が論理的に考えることが得意かを判断するには、「事実に基づいて考え判断することが得意か」という点を考慮してみると良いでしょう。
公認会計士に向かない人材
公認会計士に適した人材がいる一方で、適していない人も存在します。公認会計士は専門職であり、他のビジネス職と比べて向き不向きが明確に分かれる傾向にあります。
ここでは公認会計士の仕事に適さない人の特徴を紹介します。これらに当てはまる場合は、他の職業を探求することを検討することが重要です。
十分な勉強時間を確保できない方
公認会計士は非常に難関な資格であり、合格するには2500〜3500時間(※3)もの大量の勉強時間が必要とされます。既に働いている人にとって、このような膨大な時間を確保するのは困難です。そして残念ながら、十分な勉強時間が取れない人ほど公認会計士の勉強を途中で挫折する可能性が高い傾向にあります。
実際、2022年度の合格者の内訳において「会社員」はわずか6.5%(※4)に過ぎませんでした。仕事をしながら3000時間以上の勉強を行うためには、2年間毎日6時間ほどの勉強が必要です。このような状況下で公認会計士を目指す場合、勉強と仕事を両立させるための強い意志力と体力が必要でしょう。さらに予備校に通う時間を確保することも難しく、学習効率の低下やモチベーションの低下が懸念されます。
(※3)参考:2022年度公認会計士試験の合格者発表に関する要約
(※4)参考:2022年度公認会計士試験の合格者発表に関する要約
給与だけを重視する方
公認会計士の給与は一般的な給与所得者よりも高額であり、これが公認会計士を志す動機になることがあります。しかし、給与だけを追求する人は、公認会計士に向いていないです。
公認会計士になることは容易ではありません。数千時間もの勉強を積み重ね、公認会計士になっても業務はハードで責任が伴います。給与だけでなく実際の業務内容や忙しさなどを理解していないと、仕事との適合性に問題を抱えることがも多いです。
長期間にわたり困難な内容の勉強を行わなければならないため、実際の業務内容を十分に把握することも重要でしょう。
公認会計士の未来展望
公認会計士は合格が難しく、高い収入と多様なキャリアパスが魅力です。国家資格であることからも、今後も需要が高い職業と言えます。しかし、近年の社会動向により、公認会計士の業務や必要な知識も常に変化しています。
ここでは長期的な視点から、公認会計士が将来に向けて注視すべきポイントを2つ説明します。
コンサルティングの重要性
監査業務はAIによって取って代わられると見られています。これにより、公認会計士の事務業務は減少し、AIではできない専門家としての判断が重視される業務が中心になるでしょう。
企業は働き方や業務改善に関してコンサルタントのアドバイスを求めており、公認会計士の知識を生かしたコンサルティング業務の需要は今後も増えることが予測できます。特にFAS(ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス)や戦略コンサルティングなどの領域では、公認会計士のスキルや知識が重宝されます。
公認会計士の持つコミュニケーション能力や論理的思考力も同様に役立ち、習得したスキルが無駄になることはありません。
AI技術の習得が不可欠
現在、企業のIT化が進み、会計においてもIT統制システムが利用されています。監査を担当する公認会計士はクライアント企業の経営状況や資金の流れを正確に把握する必要があり、これらの知識が求められます。また、コンサルティング業務においても、AIやデータサイエンス技術を取り入れることで多角的なデータを活用できます。
AIは公認会計士の業務を補完し、効率化を促進するツールとして活用される見込みです。仕事がAIに置き換わるのではなく、AI技術を理解し活用できる公認会計士が将来的に重要な役割を果たすと予想されます。将来的に公認会計士として長期的に活躍するためには、AIの進化に適応し新たなスキルや知識を身につけることが必要です。
公認会計士を目指す際に押さえておくべきこと
公認会計士は将来性があり、多岐にわたる分野で活躍できる仕事です。高い給与と多様なキャリア選択肢から、多くの人が憧れる職業でしょう。
しかし、一方で「公認会計士は向いていない」という声もあるのには理由があります。自分自身の適性や目的、資格取得後の働き方をじっくりと考えずに公認会計士を目指すことはおすすめできません。
公認会計士にはどんな能力が求められるのか、公認会計士としての仕事内容や労働環境はどうなるのか、さらに公認会計士試験に向けて何千時間もの時間と努力を惜しまなければならない覚悟があるのか、ということをよく考える必要があります。合格できないこともあるからです。後悔することなく、試験勉強を始める前に情報収集をして、自分が本当に公認会計士になりたいと思うのかを吟味しましょう。
それでも公認会計士を目指すと決意した場合は、強い意志を持って知識の習得に取り組んでください。ただ試験合格を目指すのではなく、公認会計士としての業務内容や将来のキャリアパスも見据えることが大切です。
公認会計士の転職なら「WARC AGENT」の無料カウンセリングへ!

「WARC AGENT」なら、大手上場企業からIPO準備企業のベンチャー求人まで幅広く対応しています。
業界トップクラスの転職実績もあり、業界に精通しているエージェントも多数在籍していますので、ぜひ気軽にご相談ください!
LINEで簡単転職相談もお受付しています!

LINEからお気軽に無料相談もできます!ご自身の転職市場価値を確認しましょう。
