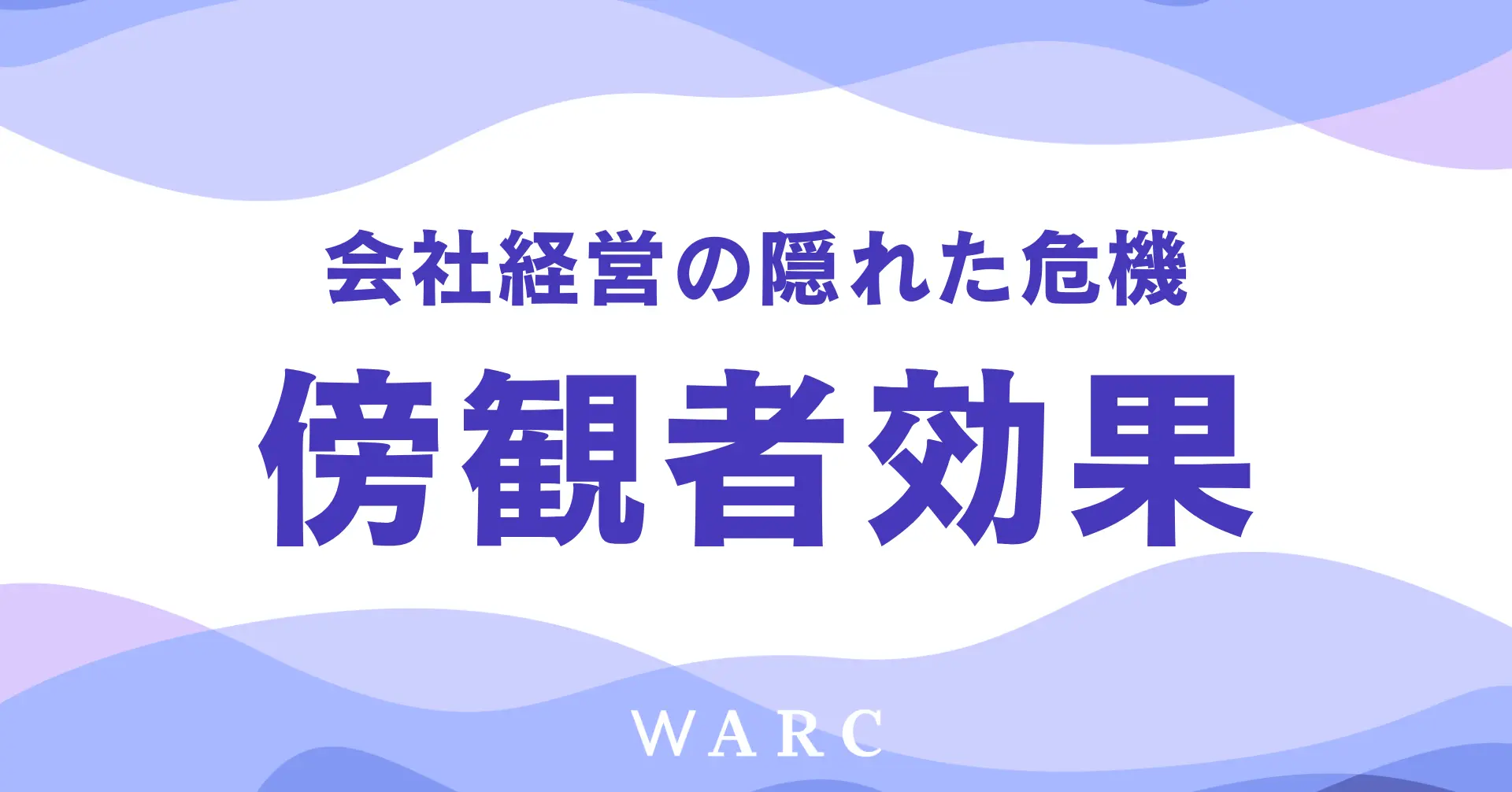
経営の危機を招くかもしれない「傍観者効果」について解説します
自分の目の前で起こった事故や出来事に対して、即座に対応しないといけないのに、周りにたくさんの人がいることでなかなか動けないときがあります。
これを傍観者効果と言いますが、ビジネスの世界でも頻繁に発生しています。
本記事では、この傍観者効果の原因とその防止策について考えてみたいと思います。
はじめに
本連載では、ビジネスで活用できそうな心理学理論や重要なキーワードをご紹介しております。
今回は、会社組織の中で頻繁に起こることであり、かつ、深刻な損害を招きかねない現象である「傍観者効果」を解説いたします。
1.傍観者効果とは
傍観者効果とは、集団心理の一種で、突発的な事件や出来事が発生した際に、自分以外に多数の人間がいる場合には、人間は率先した行動を起こさないという現象のことをいいます。
英語では “Bystander Effect” といいます。
この分野の研究は未だに続いていますが、最初の研究は1964年にニューヨークで発生した殺人事件(キティ・ジェノヴィーズ事件、以下「キティ事件」といいます。)が基となっています。
あまりに凄惨な事件なので詳述することは避けますが、重要な点は目撃者が複数人いたにもかかわらず、誰も警察に通報しなかったという点です。
当時、マスコミはこの事件を大々的に取り上げ「冷淡な都会人」という内容で記事を書き続けました。
一方で、この事件に興味を持った心理学が2人いました。
一人目がラタネ博士(Bibb Latané, 社会心理学者)、二人目がダーリー教授(John Darley, 社会心理学, プリンストン大学, 元アメリカ心理学会会長)です。
この2人はキティ事件について、メディアとは違う視点から考察していきました。
すなわち「目撃者が多数いたのに誰も警察に通報しなかった」のではなく「多数の目撃者がいたからこそ、誰も通報しなかったのだ」という視点です。
その後この仮説について実験を繰り返し、傍観者効果を提唱するに至っています。
2.傍観者効果の原因
なぜ人は自分以外の誰かがいれば傍観者効果にのまれてしまうのでしょうか。
本来、緊急時には自分で行動しなければならないとわかっているにもかかわらず、どうして率先した行動を起こさなくなってしまうのか。
この点については、以下の3つの要因があるのではないかと考えられています。
- 多元的無知
- 責任分散
- 聴衆抑制
以下、それぞれ説明いたします。
(1)多元的無知
多元的無知とは、集団内の個人が、自分自身は集団規範を受け入れていないにもかかわらず、他の人がその規範を受け入れていると信じている状態のことをいいます。
何を言っているかわからないと思うので、事例を見て学んでいきましょう。
例えば、とある学校の中で火事が起こったとします。
この場合、普通は火事の現場から遠ざかる方向で避難しますし、それが常識的な方法です。
しかし、実際の火事の現場では、より危険な方向に向かって集団で移動してしまうことがあります。
どこで火事が発生したのかよくわかっていないような状況では特に起こりやすいことです。
このような状況下で、集団移動している最中の個人は、その避難行動が正しいかどうかわかっていません。
それにもかかわらず「皆があちらに向かっているからきっとこっちが安全なのだろう」という思い込みをしてしまいます。
しかも、この思い込みを集団で起こすのです。
これが多元的無知です。
日本で起こった誘拐事件などでも多元的無知は発生しています。
ある日、とある町で小学生が誘拐されました。
そして、その子どもが連れ去られたその現場には大勢の人間がいて、目撃者も多数存在したのですが、誰も通報しなかったのです。
このケースも多元的無知の発生事例で、他の誰も騒いでいないし、通報などもしていないから、きっと知り合いの人だったのだろうと、その場にいた全員が思い込んだわけです。
幼い子どもを抱えている世帯の皆様は、この恐ろしさがわかるはずです。
周りにどれだけ大人が存在しても、多元的無知が発生してしまった時点でアウトです。
しかも恐ろしいことに、このような事件は日本でも複数件起こっています。
実は私の地元でも昔同様の事件が発生したことがあります。
近所の公園で女児が誘拐され、その当時その公園には目撃者が10名以上いたのですが、誰も警察に通報していませんでした。
その日の夜、娘が帰ってこないということで両親が警察に相談し、その時点で初めて発覚したのです。
数日後にその子は開放され、同じ公園内で無事に発見されましたが、犯人が捕まったという話は聞いていません。
(2)責任分散
続いて、傍観者効果の原因として、責任分散があると考えられています。
責任分散とは、大勢の人間がいる場合に、責任が分散することで自分が負うべき責任が軽減されることをいいます。
簡単にいえば「きっと誰かが何とかするだろう」という心理状態に陥ってしまう現象です。
この現象は、人数が多ければ多いほど発生し、かつ、日本では文化的に特に発生しやすいだろうと思います。
日本人は控えめでリスク回避傾向が強いという性質を強く有するため、他に多数の人間がいるような状況では、わざわざ自分から前に出てリスクを冒すということをしません。
自分ひとりがその他大勢と違う行動をとってリスクを冒すより、大勢で一緒に失敗した方が負う責任も軽くなるからです。
(3)聴衆抑制
最後に、聴衆抑制も傍観者効果の原因の一つであると考えられています。
聴衆抑制とは、自分以外の人間たちからのネガティブな評価を恐れるがゆえに、行動が抑制されてしまう現象のことをいいます。
例えば、自分の目の前で誰かが倒れてしまった場合に、他にも沢山の人がいる中で、迅速に呼吸及び心肺停止状態の確認、心臓マッサージまたはAEDの手配、救急車の連絡などを迅速に行なえますでしょうか。
沢山の人間がいる中で自分がその行動を率先して行った結果、その人が死んでしまった場合、どういう評価を受けるでしょう。
仮に倒れたのが女性で、自分が男性だった場合、心臓マッサージをしたり、AEDをつけたりする作業を行うと、他の女性からネガティブな評価を受ける可能性があったりするのではないでしょうか。
他にも、迷子になっていると思われる女の子に対して、声をかけるべきか悩んだ場合、周りにたくさんの人がいたら、自分へのリスクを回避するために見て見ぬふりをすることが正解だと思ったことはありませんか。
特に男性の場合は、女児に話かけるなんてリスクが高い行為をなかなかできないはずです。
もし救命活動に失敗したら、もし迷子でも何でもなかったら、周りの人からネガティブな評価を受ける可能性がありますし、下手をすると通報されかねません。
ここでの最善策は、その場をそっと離れることだと考えるのも無理はありません。
これが聴衆抑制です。
上記のような原因が単体または複数同時に発生することで傍観者効果が発生してしまいます。
そしてこの現象はプライベートな事例だけでなく、ビジネスの世界でも頻繁に発生しています。
経営に重大な影響を及ぼすようなアクシデントが発生していても、他の誰かが報告するだろうと思って上層部にまで報告が上がらないケースなどがよくある事例です。
このような傍観者効果を放置してしまうと、知らない間に損害が拡大してしまうこともあり得ます。
3.傍観者効果の防止
ではどうすれば傍観者効果を防止できるのでしょうか。
この点について考えていきましょう。
(1)多元的無知の抑制
多元的無知は、多くの人間が集団で誤った行動をしてしまう現象です。
これに巻き込まれないようにするためには、まずは思考停止に陥らないことです。
周りの人間がそう動いているからといって、それが正しいとは限らないということを常々意識しておきましょう。
すべてのことを疑えとは言いませんが、頭の片隅に「今の行動は間違っているかもしれない」という考えを置いておくべきです。
例えば以下のような思考です。
- この避難経路は客観的事実に基づいていないかもしれない
- 誰も警察・救急に通報していないかもしれない
- このプロジェクトにはそもそもニーズがないかもしれない
- 社長が意思決定をするために十分な情報が共有されていないかもしれない
- 誰も広告の効果検証を行っていないかもしれない
など
頭の片隅に常に「間違っているかも」という思考を置いておけば、多元的無知から開放される可能性が高まります。
一度立ち止まって、冷静に周りを観察し、一段高いところから俯瞰的に物事を眺めることが必要です。
(2)責任分散抑制策
責任分散は、複数の人間に責任が分散されてしまう現象でした。
これによって傍観者効果が発生しやすくなります。
しかし、これはある意味合理的意思決定の現れでもあります。
例えば、会社内で若干面倒なアクシデントが発生していて、それについてどこの部署の誰が責任を持つのか不明確になっている場合を想定してみてください。
この場合、自分が率先して役員等に報告を上げてしまうと、自分がそのアクシデントを解決するように命じられるかもしれませんよね。
それによって出世したり、昇給したりすることが確実であるならばやる意義もあるかもしれませんが、大抵は責任だけがのしかかってきて、メリットがありません。
そのような状況下では、アクシデントの趨勢を傍観し、誰かに明確な指示を受けるまで待機するのが合理的といえるでしょう。
一般的な従業員であれば通常そういう判断をします。
これを防止するためには、責任分散を防止したい側が自発的に動くしかありません。
上記の社内アクシデントの事例でいえば、社内のアクシデントを報告してもらうことでメリットを受ける側(経営陣)が自発的行動を促すしかありません
例えば、責任分散による傍観者効果を抑制するために、報告することに対する何らかの報酬を提示するという方法があります。
報告してくれた人に報償金を出したり、表彰したりすると良いでしょう。
更に進んで、発見した問題を無事解決した人については、人事評価でプラスの評価を与えるなど、明確なメリットを提示すべきです。
それによって責任分散を抑制することができます。
人間は通常、ネガティブな報告をすることやネガティブな事象に対する改善活動をすることなどには従事したくないと考えます。
そこにあえてメリットを設けることで、一部の人間は進んで責任を取ろうとしてくれるはずです。
それによって傍観者効果をある程度抑えることができるでしょう。
(3)聴衆抑制の抑制策
聴衆抑制は、周りの人間からネガティブな評価を受ける可能性を恐れる気持ちから発生する現象でした。
ということは、ネガティブな評価を受けないという確信があれば聴衆抑制を防止できます。
しかしこれは容易なことではありません。
特に何かの問題を解決しようとする行動にはリスクが伴いますから、それに比例する形で他人からネガティブな評価を受けるリスクも高まります。
そのような状況下で聴衆抑制を防止するのは至難の業です。
現実的に考えて、よほどの使命感やメリットがない限り防止することは難しいでしょう。
先程の事例のように誰かが倒れた場合の救命活動や救助活動なら使命感を発生させやすいかもしれませんが、社内で起こる様々な問題に対する改善行動についてはなかなか難しいものがあります。
したがって、この場合でも、聴衆抑制を防止したい側(経営陣)が何らかのメリットを提示する必要があると考えられます。
ただ、私の経験上、社内の大幅な改革プロジェクトや改善プロジェクトの多くが途中で頓挫するか、改革派の主要メンバーの離職を招いています。
何らかの大きな変化を起こそうという場合、必ずと言っていいほど社内に抵抗勢力が現れるため、全力で邪魔をしてきます。
その精神的ストレスに耐え続けられるほどの人はそもそも少数派です。
経営陣が全面的にサポートしつつ、かつ主導的な行動を取り続けない限り、従業員だけで成し遂げるのは困難であると思います。
おわりに
ということで今回は「傍観者効果」について解説させていただきました。
傍観者効果の発生原因を知っていれば、組織を意図的に変えていき、傍観者効果が発生しづらい組織に作り変えることも可能です。
何かが起こってしまってからでは遅いので、心理学の知識を上手に活用して、組織を作ってください。
また、ビジネスの世界だけでなく、家族もある意味組織です。
家族の中ですら、傍観者効果は発生しますので、親の世代の皆さんはくれぐれも注意してください。
不登校、いじめ、学生の鬱など、様々な場面で傍観者効果が発生しています。
子供のためにも、一度立ち止まって観察してみてください。
今まで見えていなかったものが見えるかもしれません。
では、また次回の記事でお会いしましょう。
【お問い合わせ】
WARCで働きたい!WARCで転職支援してほしい!という方がもしいらっしゃれば、以下よりメッセージをお送りください。
内容に応じて担当者がお返事させていただきます。
